2023年10月に「吉田茂に飲んでもらいたいミルクティブレンド」という商品を作り、その後「西行法師に捧ぐ 旅疲れを癒すほうじ茶(現西行法師に飲んでもらいたいほうじ茶)」を2023年12月に発売開始しました。
大磯町にある明治記念大磯邸園の「旧大隈重信別邸・旧古河別邸」「陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸」が2024年11月23日より一般公開されています。
それに合わせ、(お茶の店ニルマーネル店主の趣味で)「大隈重信に飲んでもらいたい上級緑茶」「伊藤博文にのんでもらいたい番茶」を新しくリリースしました。
同時に「西行法師に飲んでもらいたいほうじ茶」ということでパッケージや価格などをリニューアルしています。
吉田茂に飲んでもらいたいミルクティブレンド
松本順に飲んでもらいたいミルクティブレンド
大隈重信に飲んでもらいたい上級緑茶
伊藤博文に飲んでもらいたい番茶
西行法師に関しましては内容は変わらず、パッケージと価格のリニューアルとなります。
誠に勝手ながら原材料、包材等の価格高騰により、値上げをさせていただくことに致しました。
なお、こちらの商品のティーバッグは不織布タイプを使用しております。
ご愛顧いただいている皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
西行法師について
西行法師(1118年~1190年)は平安時代末期から鎌倉時代を生きた僧であり、歌人です。
元々は鳥羽上皇に使える北面の武士であり、俗名は佐藤義清(さとうのりきよ)と言います。
平清盛は北面の武士の同僚であったそうです。
23歳で家族を捨て出家した後、全国を行脚し2300首もの歌を詠みました。
※西行が出家した理由は諸説あり
「願はくは花の下にて春死なん そのきさらぎの望月のころ」
最晩年は河内国(現在の大阪府)弘川寺に庵居し、1190年75歳の生涯を閉じます。
武士であった頃は弓の名手と名高く、源頼朝に弓馬の話を細かく尋ねられたことがあるという記録が「吾妻鏡」には残っているそうです。
鎌倉鶴岡八幡宮で今も行われている流鏑馬神事は西行法師に関連しているとのこと。
その起源について「鎌倉観光公式ガイド」では、以下のように書かれています。
この流鏑馬を始めるにあたって
頼朝は1186(文治2)年
鎌倉を訪れた西行法師(※3)に
その故実を詳細に尋ねたといわれています。
流鏑馬を行うことによって八幡宮への信仰を深め
鎌倉武士の精神的結びつきを強めようとしました▼引用:鎌倉観光公式ガイド
詳細は不明にせよ、長らく言い伝えられていることですので西行法師が何かしらの関係があったと考えられます。
武士のトップである源頼朝に尋ねられたということは、西行法師が流鏑馬について詳しく、また名の知れた人であったことがうかがえます。
大磯町鴫立庵と西行

現在の鴫立庵があった辺りに立ち寄った際「心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮れ」という和歌を詠んだ言い伝えに基づき、江戸時代に入ってから西行を慕う者たちによって鴫立庵が形作られていきます。
江戸時代(1664年)に崇雪(そうせつ)という人物がその西行の歌にちなみ、この地に草庵を建てたことから始まります。
※「湘南」という言葉の発祥もこの崇雪に関係しています。
のちに鴫立庵の初代庵主となった大淀三千風(おおよどみちかぜ、1639年‐1707年)は「円位堂」(円位は西行の僧名)を造り、鉈づくりの西行座像を安置されたと言われています。
こちらは現在も見ることができます。(↓写真)
大磯町鴫立庵は日本三大俳諧道場のひとつとなっています。
毎年3月には西行祭が行われ、献詠俳句や短歌の募集なども行われています。
詳しくは鴫立庵のHPをご覧ください。
また、他にも西行法師と銀猫の話に基づいた碑なども鴫立庵にございます。
是非拝観の際にご覧ください。

西行法師は茶を飲んでいたのか?
今回「西行法師に捧ぐ 旅疲れを癒すほうじ茶(現「西行法師に飲んでもらいたいほうじ茶」)」を出させていただくために当時のお茶事情について少し調べてみました。
平安末期から鎌倉時代初期、西行法師はお茶を飲んでいたのでしょうか。
西行法師が亡くなった数十年後、宋から戻った栄西禅師が源実朝に「茶」と「喫茶養生記」を献上したとされています。(1200年代に入ってから?)
西暦800年代には唐に渡っていた永忠や最澄らによってすでに茶は中国から日本に渡ってきているものとされていますが、どういったルートでどのように伝播していったのか等の一次資料はなく、研究者による調査が進められています。
まず栄西自身は、『喫茶養生記』上巻「六 茶調様」において、「我が国の人は、茶を摘む方法を知らない、だからこれを用いない」と書いている。つまり、栄西の知る限りでは、日本には茶の木はあるが、茶を一般には利用していない、飲用していなかったことになる。
また、建保二年(1214)二月、栄西は、鎌倉将軍家加持のため大倉御所に参上していたが、将軍源実朝が二日酔いとの話を聞き、住持をつとめる寿福寺から茶一盞と『喫茶養生記』一巻を取り寄せ、それを実朝に献上したところ大変に喜ばれたとある。この話を見るかぎり、茶については、鎌倉の将軍さえもよく知らなかったということになる。ましてや庶民はその存在を知る由もなかったことだろう。
このように鎌倉時代前期には、茶はいまだ一般には広まっていなかったのである。▼引用:日本茶の歴史 橋本素子著 淡交社
西行の少し後に生き、茶祖と呼ばれる栄西が現れた頃はまだ茶は一般的ではなかったようです。
鎌倉将軍源実朝でさえ茶に馴染みがないということは、たとえ鳥羽上皇に仕えた才ある武士であったとしても、残念ながら西行法師が茶を日常的に飲んでいた可能性はないと考えます。
いつ頃から庶民が茶を飲むようになったのかはわからないものの、日本中に「干すだけ」「炙るだけ」というような簡単な番茶が各地に残っています。
また「焼き茶」というものも存在します。
ここでもうひとつ、きわめて素朴な利用法を紹介しておこう。それは、地域によっては焼き茶と呼ばれる。山野において茶葉の用意がなかった時、身近な茶の枝を折り取って焚き火で炙り、薬缶で煮出す方法である。林業者の間では今でも当たり前のように行われているのだが、当たり前であるだけに当事者たちにとっては何も意識することはないし、市井に住む人の目にはとまらない。
▼引用:民族文化ライブラリー 番茶と日本茶 中村羊一郎著
今のように蒸して、揉んで、乾燥させる、というような製法が生まれたのはもっとずっと後、江戸時代に入ってからのことです。
もし万が一チャノキが伝来してきており、家(もしくはどこか山の中など)にあったとして、当時の人々はそのまま炙ってから煮だす(焼き茶)くらいしかできないのではないかと思います。(もしくは釜などで炒ってから煮だして飲む)
とにもかくにも、西行法師が日常的にお茶を飲んでいたとは考えられそうもありません。
西行法師に飲んでもらいたいほうじ茶のコンセプト
西行法師の時代には茶は日常的に飲まれていない、というところからコンセプトを考えました。
私(ニルマーネル店主)が西行法師に出会った場合、まずどんなお茶を出すだろう。
西行法師は長らく旅を続け、あちこちに伝説を残しています。
今の鴫立庵にふと足を止め、入ってきたとします。
長旅で空腹かも知れません。
きっととてもお疲れでしょう。
まずは香りよく、心も体も温まるほうじ茶をお出ししたいと思いました。
あれば素朴なお菓子も少しつけて。
感謝の言葉を述べ、笠と杖を置き、温かい湯飲みを両手を温めながら縁側に腰掛ける西行法師。
ほっとひと息、旅の疲れが癒えますように。
お勧めの淹れ方

2.5gの茶葉入りティーバッグが3個入っております。
マグカップを温め、ティーバッグ1個を入れ、180㏄程度の熱湯を注ぎ1分お待ちください。
もう少し長めに抽出すると味わいがしっかりします。
濃い味がお好みの方は2分~3分程度抽出してください。
こちらは鴫立庵にて販売をしていただいております。
拝観のついでにご覧いただけますと幸いです。
また、大磯町内の他のお店でもお取り扱いいただいております。
大磯町のお土産としてお使いいただければ嬉しいです。



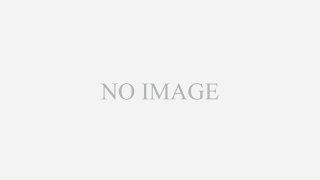
コメント